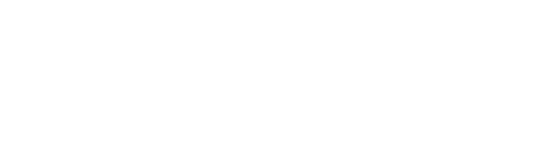2025-07-31 19:25:06 配信
津波注意報すべて解除も…「311」教訓は生かされた?
 11時間に及ぶ津波警報が出された列島。200万人以上に避難指示が出されましたが「311の教訓」が生かされた一方で、新たな課題も見えてきました。
11時間に及ぶ津波警報が出された列島。200万人以上に避難指示が出されましたが「311の教訓」が生かされた一方で、新たな課題も見えてきました。ビーチには、日常が戻ってきました。
津波注意報が解除された和歌山・白浜。観光客からは喜びの声が上がります。
神奈川からの観光客
「おととい来て1泊2日のつもりが、1泊のびて2泊3日になった。うれしいよね」
紀州・白浜温泉むさし 女将 沼田弘美さん
「解除になって、また海に行けるということで安心で安全にお越しいただける状況。またお越しいただければ」
気象庁は、夕方になり津波注意報をすべて解除しました。
茨城県・大洗港。津波注意報の影響で沖合で19時間ほど停泊していたフェリーが入港しました。
苫小牧港から乗船
「船長が適宜アナウンスしてくれて、非常に皆、安心した感じで、晩ごはんも朝ごはんも全部出て」
ただ、海水浴場の閉鎖も相次ぎ、観光地への影響は小さくありません。
江の島でマリンスポーツを提供する施設。予約はすべてキャンセルになりました。
ちょっとヨットビーチマリーナ江の島 本間桃佳さん
「夏休みで一番観光地として盛り上がる時期なので、営業できなかったりで影響はかなり大きいのでは」
千葉県鴨川市のホテルも部屋はすべてキャンセルに。
EARTH TREE CAFE 松田佐知子さん
「朝から海沿いが全然違う景色、本当に閑散としている状況。自然災害なのでしょうがない」
■「東日本大震災」の教訓・課題は?
各地に到達した津波。直接的な被害も出ています。
宮城県気仙沼市では、カキの養殖いかだが転覆するなどの被害が確認されました。
養殖業者
「311の津波で何もなくなった状態から、今ここで新しいいかだを入れてやっと落ち着いてきた矢先で、本当にダメージが大きい」
よみがえる“311”の記憶。避難所で一夜を過ごした人も…。
避難した人
「体はちょっと痛かったけど、5時間くらいは寝た。置いていただいて、皆よくしてくれてうれしかった」
その教訓もあり、多くの人々が警報が出た直後から高台に避難しました。
避難した人
「東日本の時を思い出した。地震はなかったが、とりあえずいち早く高台に上がろうと思った」
一方、SNSでは、こんな意見も…。
SNS
「今までは『津波警報は多少大げさでもいい』と思ったけどきょうのはさすがに『過剰だし熱中症の方が危険』と思った」
「経済活動止めるほどのこと違うやろ。やりすぎ」
生かされた教訓と、見えてきた課題。被災地は、この津波をどう見たのでしょうか…。
突然の津波避難に生かされた東日本大震災の教訓と、見えてきた課題を東北3県と中継を結びお伝えしていきます。
まずは岩手県久慈市にいる中森至アナウンサーです。
久慈市では1メートルを超える津波を観測しましたが、過去の教訓はどう生かされていたのでしょうか。
(中森至アナウンサー報告)
東日本大震災の教訓があったからこそ迅速な避難につながったと感じました。
津波注意報が発表されてからすぐ、避難指示は出ていませんでしたが、近くの高校に自主避難する人たちが多くいました。
また、民間企業など団体で避難する様子も見られ、誰一人も取り残さない、そんな思いも感じました。
実際に東日本大震災を経験していない子どもたちも先生の指示に従って速やかに行動していたというお話もうかがっています。
(Q.東日本大震災を経験していない子どもたちにもどうやって危機感は共有されていたのでしょうか)
私は小学3年生の時、東日本大震災を経験しているのですが、震災が起きる前、形式的な避難訓練が段々と雰囲気も含めて実践的な避難訓練に変わっていき、それが危機感への共有ができていることにつながっているのだと感じています。
今も地域で震災を経験した人たちが津波の恐怖を伝えている、今回取材をして改めて経験を伝え継承していくことの重要性を改めて感じました。
続いて宮城県石巻市には松本龍アナウンサーがいます。今回の津波で見えてきた教訓、課題はありますか。
(松本龍アナウンサー報告)
想定を超える長時間の避難、そして猛暑というところから課題が見えてきました。
石巻市の日和山公園には30日、一時100人を超える多くの人が避難してきました。ただこの場所は、いわゆる指定避難所ではなく、一時的に避難する緊急避難場所という場所で、長時間避難するための設備というものは整っていません。
そのため30日のように津波警報が長時間にわたると、避難してきた人からは「いつまでここにいればいいのか」とそういった声も聞かれました。
(Q.猛暑のなか長時間にわたる避難となったが、こうした一時避難先で備えは進んでいるのか?)
実は地元のボランティア団体が数年前からこの場所に発電機、テント、夏用のスポットクーラーなども用意していて、実際に使ったのは30日が初めてということですが、ある程度の備えが30日は発揮されたという形になりました。
30日はたまたま猛暑のなか、津波警報が来ました。ただ次は大雪の中、大雨の時に来るかもしれません。
一時的な避難場所であっても、こういったある程度の長い時間避難することができるような備え、そういったものが必要になってくるかもしれません。
続いては福島県いわき市です。樋口陽一アナウンサーに聞きます。新たに見えてきた課題などはありますか。
(樋口陽一アナウンサー報告)
どうやって避難先に行くのか、そこに大きな課題を感じました。
30日、いわき市では海側の店舗が営業せず、国道が通行止めになった影響もあり、内陸に向かう幹線道路に車が集中して渋滞が発生しました。行政は津波の避難には原則車を使わないようにと呼び掛けています。
一時避難先の高台には徒歩で行くこともできます。ただ、避難所ともなれば数キロ先、歩けば半日、一日の避難にもなることも考えられます。
さらに、昨日の暑さもあって車で避難する人が増えたとも考えられます。
30日だけではなく、東日本大震災以降も津波警報が出された際、いわき市内では渋滞が発生しているという状況です。
(Q.特にご年配の方など、車でないと避難できない人も大勢いて難しい問題だと思うが、行政としてはどんな対応をしているのか?)
いわき市はこういった避難する時に渋滞が発生するという状況を受け、2017年から会議を開き、ライフラインをまとめています。
ただ、会議の中では原発事故が起きた県内では車で避難する人が増えることが想定されるなどの意見もありました。
その一方で、市は津波に対してはとにかく早めの避難とハザードマップの通知を徹底していきたいと考えています。
LASTEST NEWS